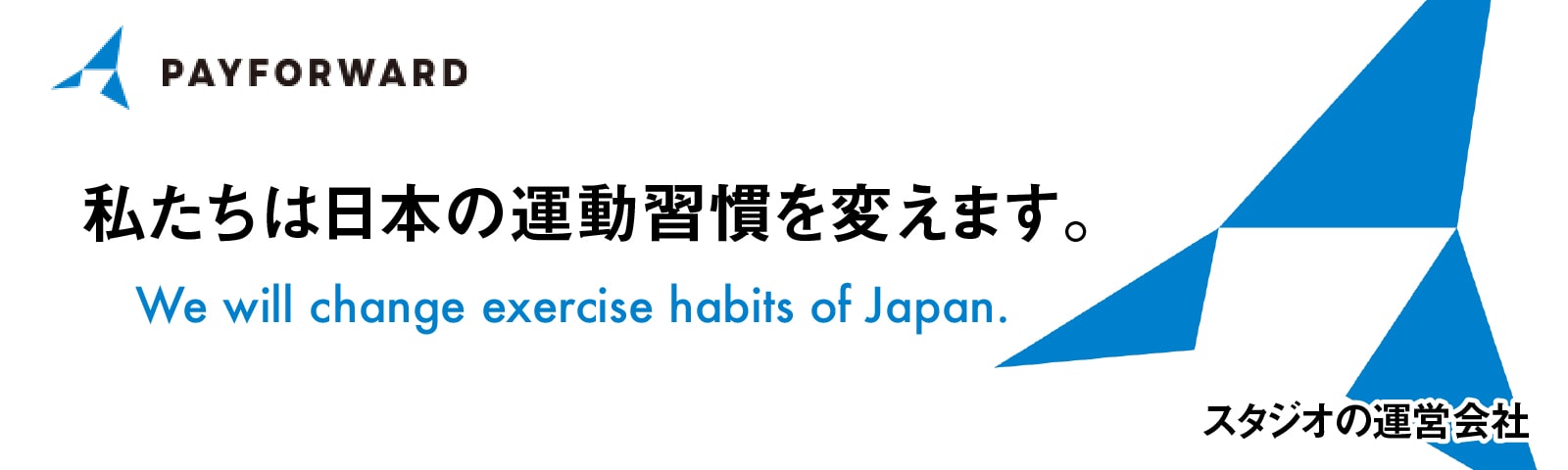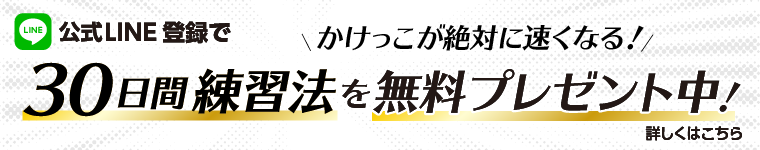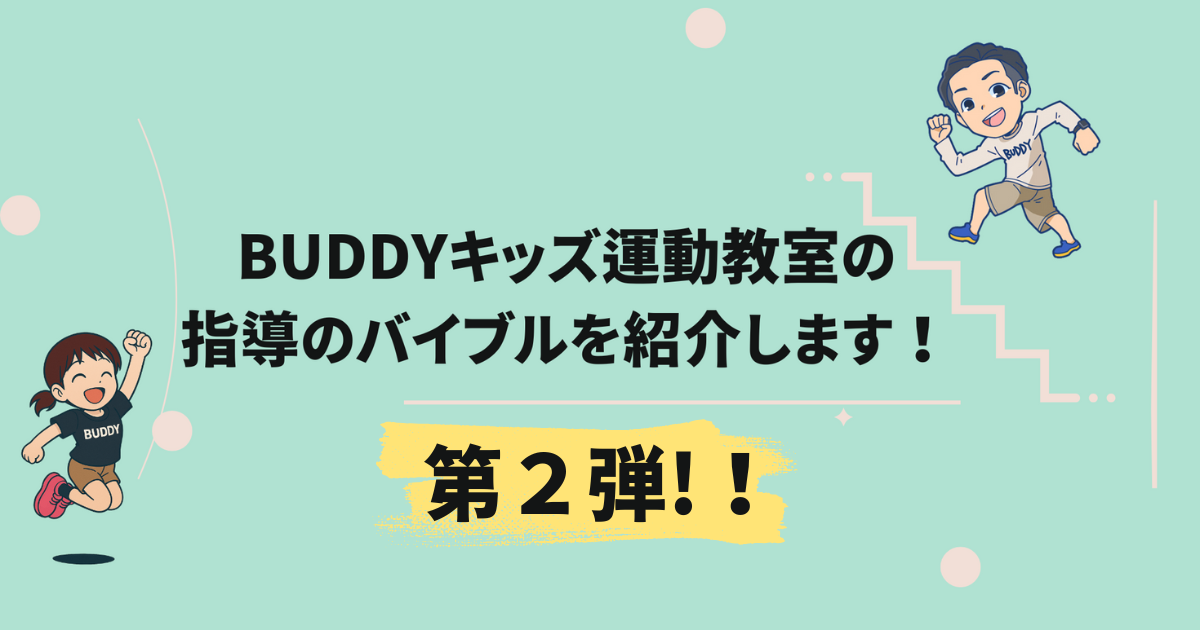
「なんとなく動く子」を育てない——BUDDYキッズの“授業の原則10か条”【後編】
こんにちは!東京都港区西麻布にあるBUDDYキッズ運動教室のくるみ先生です。
実は私、中学校と高等学校の保健体育の教員免許を持っています。
でも、教員になる道を選ばず、今は“教室”ではなく“運動教室”で、子どもたちと向き合う毎日を過ごしています。
「学校の先生にはならなかったのに、なぜ授業の本をバイブルにしているの?」
そう思われる方もいるかもしれません。
でも、“教える”ということの本質は、教科や場所を問わず同じだと私は思います。
子どもが、「分かった!」「できた!」「楽しい!」と感じられるように、その一瞬のために、どう導き、どう声をかけ、どう場をつくるか。
その指導技術のエッセンスが詰まっているのが、向山洋一さんの著書『授業の腕を上げる法則』でした。
今回は、前回ご紹介した「授業の原則10か条」の後半5つをBUDDYキッズでの具体例とともにご紹介していきます!
⑤細分化の原則
「高い跳び箱を跳べたらすごい!」それは確かにその通りですが、跳べなかった子に「さあ、跳んでごらん」と言うだけでは、子どもは前に進めません。
一つの行動を、より小さな単位に分けて、ていねいに教えること。
これができるかどうかが、プロの指導者とアマチュアの分かれ道です。
たとえばBUDDYキッズで跳び箱を教えるとき、いきなり「跳んでみよう」とは言いません。
・跳び箱の前に立つ
・両手をしっかりつく
・お尻を高く上げる
・UFOで頭を前にする……
このように、一つの動作をいくつかに分けて、それぞれを練習しながら、全体を組み上げていきます。
このような細分化は、子どもにとって「やってみたい」「やれそうかも」という気持ちを引き出すだけでなく、「なぜできたか」を自分で理解する手助けにもなります。
向山洋一先生は言います。「細分化して、解釈して、イメージ化せよ。」と言います。
それを分かりやすく、具体的に伝えることが、指導の質を高める鍵なのです。
BUDDYキッズでは、「どんな子も成功させる」ために、指導を細かく分け、段階的に積み上げていくことを大切にしています。
⑦空白禁止の原則
レッスンの中で誰かがいち早く課題を終える場面がよくあります。そんなとき、“じゃあ座って待っててね”と空白をつくってしまうと
やることを失った子は落ち着きをなくし、やがて教室全体の集中が切れていきます。
向山洋一先生は、「授業中の個別指導は『完全にさせる』ではなく、『短く何回もさせる』を原則にせよ。」と言います。
BUDDYキッズでも、個別対応は「短く」「素早く」「何度も」を意識しています。
そして、空白をつくらないためにもっとも大切なのは「終わった子への準備」です。
たとえば毎回行っている体幹トレーニングでは、
上体起こし→足上げ腹筋が終わった子には「ブリッジ」に取り組んでもらいます。できた子には「10秒チャレンジ」、次は「片足ブリッジ」と課題を発展させています。
こうしたステップアップの仕組みがあることで、「できた子」はさらに伸び、「できない子」にもプレッシャーをかけすぎずに進めることができます。
「早く終わった子をどう伸ばすか」までが、設計できてこそ、本当の指導の腕なのです。
⑧ 確認の原則
一見スムーズに進んでいるようでも、子どもたちが本当に理解しているとは限りません。
「わかった?」と聞くと多くの子が「うん」とうなずきますが、
実際には「なんとなく」「みんながうなずいてるから」「とりあえず合わせておく」。
そんな“うなずきごっこ”になっていることも少なくありません。
向山洋一先生は、「確認の方法こそが指導者の力量である」と言っています。
BUDDYキッズでは、言葉ではなく“行動”で確認する方法を大切にしています。
たとえば、レッスン冒頭で毎回行う「ボディタッチ」。
「頭・肩・胸・へそ・せなか・わき…」と、身体の部位を声に出しながら、自分でタッチしていくウォーミングアップです。
これは単なる準備運動ではなく、“身体の部位が理解できているか”を確認する重要な時間です。
その後、目を閉じて「右ひじはどこ?」「おへそは?」と問いかけると、迷う子もいます。
BUDDYキッズでは「わからなかったら、そっと目を開けて見てもいいよ」とルールを伝えています。
答えを強要せず、自分で確認する姿勢を育てる。これも確認のひとつの形です。
確認をせずに次へ進めば、「わからないまま」「できないまま」になってしまう。
だからこそ、私たちは子どもの理解を“その場で具体的に確認する”ことを徹底しています。
⑨個別評定の原則
「誰が良くて、誰がよくなかったのか」を具体的に伝える。
それが、子どもを本当に伸ばす“評価”です。
「みんなよく頑張ったね」「惜しかったね」
そんな言葉だけでは、自分がどうだったのかは分かりません。
BUDDYキッズでは、一人ひとりに向けた具体的なフィードバックを伝えるようにしています。
たとえば、くも歩きの場面では
「◯◯くんのくもさん、お尻がしっかりお空を飛んでいて、とても安定しているね!」
「△△ちゃん、手がパーでつけているのが素晴らしいよ!お尻が落ちちゃっても、すぐに持ち上げられるといいね」
このように名前を挙げて、「どこがよかったか」「どうすればもっと良くなるか」を具体的に伝えます。
BUDDYキッズのくも歩きは速さを競う運動ではありません。
正しい姿勢で、身体を上手にコントロールできているかどうかがポイントです。
こうした評価は、うまくできた子をただ褒めるためではなく、
「自分はどうだったか」を知ることで、次にどうすればいいかを自分で考えられる子に育てるためにあります。
運動が得意な子も、そうでない子も、全員がそれぞれの良さを見つけ、次の一歩を踏み出せるように誠実で具体的なフィードバックを大切にしています。
⑩激励の原則
子どもが思うようにできなかったとき、どんな言葉をかけるか。
それが、指導者としての姿勢をもっとも強く問われる瞬間です。
BUDDYキッズでは、失敗やつまずきを「伸びるきっかけ」に変えるために、
とにかく具体的に、前向きに声をかけることを大切にしています。
たとえば、鉄棒のツバメポジション。
肘が曲がってしまったり、足がバラバラになってしまったりと、初めはなかなか形が安定しません。
そんなときでも、
「肘がピンと伸びてたよ!次は足もくっつけてみようか」
「肘のピンも、足くっつけるのも完璧!次は先生の手に頭がタッチできるといいね」
など、できた部分をしっかり見つけて伝え、次の目標を添えて励まします。
できたときには、
「今のは肘がピンって伸びてたから、10秒かっこよく止まれたね!」と、
“姿勢の質”を具体的にほめるようにしています。
ただ「がんばれ」と言うだけでは、子どもは成長を実感できません。
だからこそ、「どこが良かったのか」「どうすればもっと良くなるのか」を、
具体的な言葉にして届けることが大切なのです。
できなかったことを責めるのではなく、
「次は〇〇したらできるかも」とともに考え、
「いまは、〇〇がよかったよ。次は○○を頑張ろうね」と伝え続ける。
子どもが自分の変化を信じられるように。そして、もう一度挑戦する勇気を持てるように。
私たちは、どんなときも励ましの言葉を止めません。
◆ どんな子も、必ず伸びる。その可能性を信じて。
子どもは、日々、少しずつ着実に成長しています。
昨日できなかったことが、今日ふとできるようになる——
その一歩一歩に寄り添えることが、私たちのいちばんの喜びです。
今回ご紹介した『授業の腕を上げる法則』——
細分化・空白禁止・確認・個別評定・激励という5つの原則は、
BUDDYキッズのレッスンの中でも、私が大切にしている“指導の軸”そのものです。
でも実際は、私自身もまだまだ学びの途中。
毎日のレッスンの中で、子どもたちの姿にハッとさせられ、
声のかけ方や待ち方を改めて考えさせられることばかりです。
「この子の、いちばんの理解者でありたい」
その気持ちを忘れずに、これからも一人ひとりと丁寧に向き合いながら、
指導の腕を磨き続けていきます。
教室は港区西麻布に引っ越しました!
2025年6月より、東京都港区西麻布3-23-5に移転しました。
白金高輪・広尾・六本木・麻布十番・南青山エリアからも通いやすい立地です。
「港区 子供 体操教室」「六本木 幼児 運動教室」「広尾 小学生 運動習い事」などでお探しの方も、ぜひ一度教室を体験してみてください!
体験レッスンは随時受付中です。お子さまの「できた!」の瞬間を一緒に見つけに来てください!